国民的作家による明治日本を1つのプロジェクトと見立てた大作
歴史を通じて、読書などを通じて、教養や様々な視野が身につくと言うのは様々な所で伝えられる「お約束」のような一文になっています。しかし書店でずっと売られているロングセラーの中には実際にそれだけの質・量を伴ったものがあり、ネット記事やブログ、あるいは1冊の新書だけでは伝えられないスケール感や雑多な情報を抱えた作品も、やはり存在しています。
そんなスケール感と質・量を備えた個人的にも思い入れの強い1冊が本作です。
司馬遼太郎といえば、日本を代表する歴史作家。その歴史観は昭和の時代の知識層にも多大な影響力を与え、いまの企業の創業者クラスの方が若い頃に司馬作品を通過した方はかなり多かったのではないかと思います。
例えば明治時代から既に国民的に徐々にその人気を高めていた坂本龍馬ですが、その坂本龍馬という人物がいま認識されているキャラクターで定着した逸話の数々は明治時代に(脚色されたものも含めて)たくさん出回っていた証言や逸話を膨大な書籍を買い漁って司馬が紡いだ「龍馬がゆく」で固められていったと見て間違いないでしょう。
このような国民的に影響力の強い歴史作家と言う位置づけは世界的にも珍しいらしく、稀有な作家だったと言えるでしょう。ただ、やはりネットのない時代の当時の文献に頼った部分、そして作家本人の意識もどうしても混ざってしまう為、いまとなっては解釈が危ういものが多かったり作者の主張が偏っている部分も指摘されることがあり、よく揶揄される「司馬史観」というものにも少し距離を置く必要もあるとも思います。
しかし、歴史ナビゲーターとしてはやはり、今尚魅力を放つ作品の数々を残した功績は素晴らしいものだと思います。もともと作者はエンタメ寄りの時代小説の作家だったのですがそれが歴史の語り部として認識される転機となった作品とも言えるのがこの「坂の上の雲」でしょう。
今の時代を読み解くヒントにも満ち溢れた作品
時代は明治、もともと秋山兄弟と正岡子規という軍人と作家の対比によって明治の成り立ちを語る…というコンセプトで始まった作品ですが蓋を開けると、明治と言う国家が多大な苦労や苦悩を抱えながら、列強の一員となるという1つの目標に向けてとてつもないエネルギーをもって邁進していた事が伝わります。
取られている時代が広範で、スケールも大変に大きいため、作者特有の「余談であるが」と触れてから脇役の生涯や逸話に脱線する話も相当の数に上り、このへんで冗長さを感じる向きもありますが歴史は登場人物1人1人が主役である、という作者のポリシーが徹底されているとも言えるでしょう。
そして、近代の東アジアをめぐって日本、中国(清朝)、ロシア(帝政ロシア)、アメリカやイギリスなど様々な国の思惑も交差します。このあたりはこの時代の様々な国の情勢に興味が向くきっかけになると同時にそれぞれの国のルーツに遡ってみたくもなるきっかけにもなります。
また同時に日本は昇り坂の40年を辿った後下り坂の40年を辿るサイクルがあるとも言われてもいます。それは明治の40年と終戦までの40年…「帝国主義」を目指した大日本帝国の時代と、戦後~バブル景気までの40年と失われた30年を経た平成以後の停滞期…「経済大国」を目指した戦後日本とで様々な事象が綺麗にリンクしているからです。
1つの大きなプロジェクトとしての近代国家明治の成り立ちと、その最大のクライマックスとなる日露戦争の勝利。そして後の太平洋戦争への敗戦へと繋がる悪しき日本の一面にも、しばしば触れられております。
このあたりは歴史は繰り返すと言われている通り、今に繋がる歴史の流れを通じて今の時代を読み解くヒントにもなりますし、様々な国の近代の情勢を取り巻く一大叙事詩としても、巨大な国家プロジェクトの失敗と成功のドキュメンタリー作品(ものすごくスケールの大きいプロジェクトX)としても、大変意義深い一冊となっています。
翻って、一つの歴史小説という側面とは別に、様々な示唆を含んだドキュメンタリー、経営や人生に置き換えられる教訓、地理や国家へ具体的に視野を広げる好奇心の材料としても、秀逸な小説という事になります。全8巻分は重いですが、その内容以上に秀逸な教養が身につく作品ではないかと。
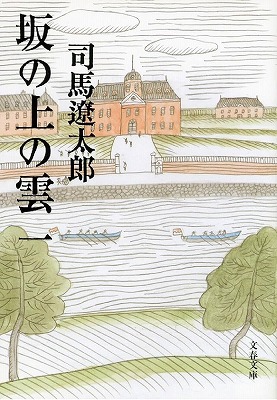



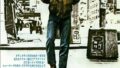
コメント