現在でも長くつづく国民的特撮番組ウルトラマン。初期は純然たるSFを至高していたシリーズですが、次第に人間ドラマやヒーローものとしての側面も強めていきました。そんなシリーズのドラマ面での原点となる作品、ウルトラマンと主人公が一体化する流れや、都市を襲う怪獣と怪獣攻撃チームの攻防を一際ドラマとして丁寧に描き切った初期の傑作シリーズがあります。それがこの「帰ってきたウルトラマン」なのです。
シリーズやその後のサブカルチャーにも大きな影響を与えた作品
ウルトラマンと言えば現在まで続編が作られる日本を代表する特撮作品。自分も昭和のウルトラマンはリアルタイムでは見ていませんが幼少期にそれに影響された世代のパロディやオマージュ…親戚からのおさがりでもらった怪獣図鑑、また長期休みで繰り返し再放送されていた事もあり大きな影響をうけたシリーズでもあります。
シリーズでは特にSFに本格的に取り組み、今なお再検証や新規出版物、映像化もなされる事の多い初期作であるウルトラQ、ウルトラマン、ウルトラセブンの「第一期ウルトラシリーズ」の評価がいまだに高く、その後、数年のブランクを置いて復活し、仮面ライダーなどの等身大特撮も隆盛を見せる中でそれらと凌ぎを削りながら「変身ブーム」の中心でもあった70年代に放送された第二期ウルトラシリーズ。
人気設定であるウルトラ兄弟と言う客演を思わせる設定が本格化したのもこの時期で、SF以上に人間ドラマや、強豪怪獣の演出や歴代主人公の客演などよりヒーローものとしての側面を強め、それこそが現在まで延々と続く国産ヒーローものやシリーズそのもののフォーマットのベースをより強固に固めたとも言えますが(本作のメインライターの上原正三は後のメタルヒーローやスーパー戦隊の初期作でも導入回やシリーズ構成から関り、脚本もまた多くを担当しそれらフォーマットを確実に固めて行った人でもあります)
やはり人気や語られる率としては、純然たるテレビSFを指向した第一期の作品に比べて、少し落ち着いてしまう点がある面も否めません。しかし、特に第二期のシリーズの最初の作品でもある帰ってきたウルトラマンはシリアスなMATチームの雰囲気や、上層部や時に隊員同士でも対立するドラマ
強豪怪獣が現れた際に後方支援の自衛隊と思しき部隊と共闘したりなど、SFやリアリティも重視していた第1期のムードを引き継ぎつつ、過去作では描かれなかった主人公の具体的な内面描写に加えてプライベートでの描写…また市井の市民から見た目線も多く盛り込んで、第1期と第2期のそれぞれの特徴をバランスよく取り込んだ作風であったように思います。
哀愁と人間ドラマを含んだ骨太な特撮ヒーロー
シリーズ中でも何かと話題になるのが「怪獣使いと少年」という差別をテーマに切り込んだ問題作(33話)。そして、その回も含んだ放送中の11月の時期に当たる5作品(31~35話)また、レギュラーキャラクターの衝撃的な退場とウルトラ兄弟の客演を交えたインパクト抜群の37,38話(事実上の最終回とまで言われる)が話題にあがる事もが多いのですが…
個人的には初期の6話までの流れや、ベムスターが登場するあたりにかけての期間が特に好きで(つまり中盤までの加藤隊長時代)そのあたりまでで主人公の成長はほぼ描き切っていた感があるのです。特に初回では、ウルトラマンと主人公の融合までのドラマを現在に至るシリーズ中でも特に丁寧に描写。
慢心する主人公の挫折と再起(2話)、主人公と隊長や隊員との対立2大怪獣とのハンディキャップマッチ(3話)、強豪怪獣を特訓の末破るスポコン展開(4話)現実の都市にもし怪獣が現れたらという展開をリアルにシミュレートした回(5,6話)。
心のすさんだ少年の再起の話(15話)都会を離れ山奥に住む少女を巡る市井の人間ドラマベースの話(12話)津波怪獣の恐ろしさを大々的な特撮を用いて描写する回(13,14話)に強豪怪獣との対決を過去作のヒーローの客演・必殺武器の導入を交えて緊張感たっぷりに描いたエピソード(18話)など
過去作にない新しいタイプのドラマを人間ドラマを軸に展開し、後のシリーズでもこれらを下敷きにしたエピソードがリファイン、リメイクされていく事になります。
夕日をバックに佇むどこか人間臭く、哀愁あるウルトラマン
MATチームや主人公の居候先である坂田家などのレギュラーも、芸達者な役者が揃いドラマとしての雰囲気が一層際立っていた感があります。黄金期のスタッフが名を連ね、SF重視だった1期を代表するウルトラセブンと並んで後々の様々な国産ヒーローと比べても、人間ドラマとヒーローものの融合を目指した王道の特撮ドラマの原点的作品にして、頂点の1つだと言える完成度を持っていると思います。
本作の主人公、郷秀樹は故郷を捨て上京し、坂田家で自動車修理工として働きながら居候、やがてMATチームと二足の草鞋の生活になり、最終的にウルトラマンと人格が融合?し、ウルトラの星へ旅立つ事になります。
その故郷の定まらない異邦人的佇まいは、どこかあしたのジョーや太陽にほえろのマカロニ刑事などに代表されるアウトロー主人公を彷彿とさせ、隊の規律より私情を優先させ命令違反も厭わない姿勢は機動戦士ガンダムのアムロ・レイの先駆けでもあり、人間と超人の狭間で悩む描写は仮面ライダーの本郷猛やデビルマンの不動明と重なる部分もあります。
つまり70年代的エッセンスが主人公に濃縮されているのですね。またMATチーム内の雰囲気も太陽にほえろを始めとした当時の刑事ドラマの署内のような雰囲気もあり、子供向けエンタメ作品の中に上層部との対立や隊員間の軋轢などを盛り込んだ内容は、後の「ガンダム」に「踊る大走査線」何より本作に多大な影響を受けたエヴァンゲリオンの庵野秀明監督が出がけた「シン・ゴジラ」(プロットも5・6話の影響が見受けられます)などに引き継がれています。
予算がなくなっていく終盤に向かうほど、ドラマ・特撮どちらの面でもやや粗い面も目立ってもきますし、古い作品特有のツッコミどころも見受けられますが(笑)
70年代当時の今では見られないエッセンスの見本市のような作品でもあり、今に繋がるサブカル作品の原点のような側面もある。それらが映像的にも役者や特撮的にもしっかりしたクオリティでまとめられているのが魅力なのです。
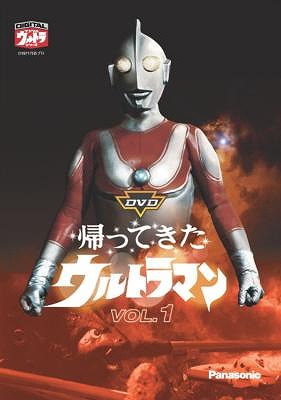




コメント