最近のゲームは複雑で、長時間で…映画のような短い時間でゲームならではの表現(インタラクティブ性)で、映画のような充実感を味わえる1本を楽しみたい。そんなニーズに応えた1本を紹介します。プレイステーション2で初出となった「ICO」です。
2001年末、古城の旅
2001年、PS1からPS2への本格的な普及期に当たる年…
ファイナルファンタジー10やメタルギアソリッド2などPS時代から引き続いた大作が続々リリースされたその年の年末に兼ねてより画面写真が公開されて、その独独なムードが密かな話題を呼んでいた本作「ICO」がリリースされました。
実際にはPS1から開発が進められていたようで、紆余曲折ありPS2のタイトルとしてリリースされる形となったようです。本作はとにかくゲームの舞台となるのが古城と言う限定された舞台であること、ヒロインとICOが写実的ではあるものの現在でいうフォトリアルともまたアニメ調とも違う独特な造形
であったこと。
本編に登場する魔物も、また全てが影の形で表示されるなど他のゲームとは違う独自性が、画面写真からもはっきり伝わってくる、感性にビンビン訴えかけてくるようなゲームでした。
そして、発売されるや国内外の特にクリエイターから絶賛され、ディレクターである上田文人はその後も「ワンダと巨像」そして大幅な製作期間の延期を経て発売された「人喰いの大鷲トリコ」など、本作と同じ独特の世界観や質感を継承した作品群によって「ゲーム界のジブリ」的な評価を得たと思っています。
その無駄をそぎ落としたゲーム性やゲームデザインは、まさに時代に埋もれない「普遍性」と「ミニマル」な魅力にも溢れています。
当時のゲーム業界の常識とは外れた、引き算のゲーム性
当時のゲーム業界の主流がコントローラーをフルに使った複雑な操作体系、やり込みユーザーに向けた膨大なおまけ要素、ゲームとして動かせる本編と切り離せるくらい長時間にわたるCGによるムービー表現などなど、どんどん表現がコアユーザー向けに傾いている懸念がありました。
そんな時代にあえてパラメーター表現もなくし、ムービーによる表現は最低限、ストーリーも多くは語られず、クリア後の追加要素もわずか。本編のプレイ時間も決して長くはない…という本作の作風はかなりの「冒険」であったように思います。
その分、多くを語らない本編をプレイヤーは脳内補完することが出来、複雑な操作がない分プレイヤーを選ばず、本編が短い分一本の良くできた映画を鑑賞するような気持ちで(操作体系がシンプルな事もあり)再プレイしやすいという旨味があります。
ルーツとなる作品群と後続への影響革新的だったアート性と独自のゲームデザイン
本作のルーツとしては無人島にいきなり投げ出されて島の中にある本やメモ帳などのヒントを頼りに無数のオブジェを弄ったり、計算したりしながら先へと進めていく「MYST」があると思います。リアルな挙動のキャラクターがヒロインを助けながら城から脱出するというコンセプトはまた「プリンスオブペルシャ」を思い出したりもしました。
どこか日本ではなく洋ゲーからのフィードバックを強く感じさせる作風なのです(上記はどちらも海外産の洋ゲーでした)しかしヨルダの造形や、その透明感ある雰囲気などはヨーロッパ的でありながら日本的な「儚さ」もあってこそ表現しえたものかもしれません。イコとヨルダの関係は銀河鉄道999の鉄郎とメーテルを思いおこさせる所も。
そして謎解きゲームの文法としてはゼルダの伝説など、国産の謎解きアドベンチャーの系譜をばっちり引き継いでもいます。
革新的だったアート性と独自のゲームデザイン
本作独自の革新的だと思えるものが、まずゲーム内の環境音に徹底的に拘った事です。これによりゲーム内のエモーショナルな雰囲気がより高まっていたように感じます。
そして、高低差をしっかり描いた「リアルな」古城のサイズ感。建築物として徹底的にリアルなサイズに拘っているように感じました。現実にありえそうといよりは、ゲームとしての楽しさと建造物としての魅力が嘘くさくない程よいレベルで表現されていたという感じです。
特に高低差を感じさせるシーンでは思わず身震いしてしまうアングルのものがあったりもします。前述の効果音がその臨場感をより高めていたのですよね。
そしてようなルーツとなる作品と独自性によって確立された本作自体がまた1つのゲームの形として強いインパクトを残し、現在インディーズゲームなどで発売されているシンプルな操作感でアート的なデザインや独自の世界観を押し出した個性の強いゲーム群が(「LOMBO」や「RAIN」「風ノ旅人」など)本作をルーツとし発展していったものだと思っています。
ゲーム性は別として、アートディレクション面のみで残した影響もまた強く。光源が強く、モノトーン調に拘ったシックなデザインのメインキャラ達、人工物と自然描写の融合を徹底的に拘った点で「ニーアオートマタ」などジャンルはRPGという別分野で、シナリオや戦闘の比重が高いゲームとなりますが、アートディレクションではかなりの部分でその影響力を継承しているタイトルも後年、見受けられるようになりました。
しかし、それら後続の似たような路線にある作品群やデザイン面で影響されたタイトルと比べても尚、本作のシンプルかつ美しいデザインと透き通るような世界観は時代を経た普遍的な魅力に溢れています。
プレイ時間はそれほど長いものではないもののパッケージのゲームとしてシンプルながらしっかりと手ごたえを感じる作りにもなっていて終盤に向けてのストーリーの山場、そして切ないEDへと繋がっていきます。
続編の展開と上田ゲームと言う1つのブランド
タイトルこそ違うものの、同じ上田文人が出かけた作品となる続編的作品「ワンダと巨像」は同じようなアートデザインや世界観を引き継ぎながらも大きな敵と戦うというコンセプトや、古城に限定されていたICOとうって変わって限定的ながらも幻想的な変化に富む1つの地域をシームレスに描きだした点が非常に斬新でした。
巨大な敵もオープンフィールドもより身近になった2022年現在では、やや時代を感じさせる部分もあります。しかし「静的」なICOに対してワンダは「動的」ゲームとも言え、いい意味で対となる存在のゲームとも言えます。
「人喰いの大鷲トリコ」はゲームデザイン的に本作をより複雑化させた部分があるように感じました。トリコの造形やAIはヨルダ以上に複雑且つインパクトあるものにも仕上がっています。しかし複雑すぎる情緒を持つトリコを引き連れてICO以上に複雑で長い道中を進んでいく過程は、やや苦痛を感じさせる作りになっていたのも確か。ICOでいう影のような明確な敵の存在もありませんでした。
上田作品としての最初になる本作「ICO」はシンプル且つ描きたい部分が限定的だったからこそ、後の「上田作品」2作と比べてもよりシンプルな魅力が光るのではないかと思っています。
現在遊ぶには…
そんな名作「ICO」なのですが、プレイステーションの発売元であるSCE独自のタイトルとして発売された経緯からかマルチ展開がなされておらず、現在主流のハードで遊ぶにはプレイステーション4及び5、あるいはPC経由でPS+ Premiumに加入して遊ぶ方法しかありません。
ソフト単体としてはPS2のオリジナル版とPS3のリマスター版が存在しており、それらのハードがあれば遊べます。続編とも言える「ワンダと巨像」はPS4でリメイク版が発売されたので、本作もいつかさらなるリメイクやリマスターの動きが出る事を期待しています。。
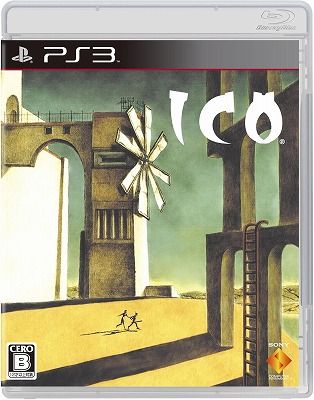

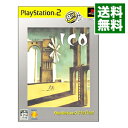

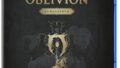
コメント