平成の時代最高のゲームに数多くのランクで1位を獲得
かつて日本を圧席していたRPGというジャンル、今でも人気がある定番ジャンルですが、それが一際輝いていた時代がスーパーファミコンの時代でした。そんな時代に誕生した金字塔的作品が本作になります。
平成の末期、ファミ通やオンラインのランキングで何が平成の最高のゲームか?というランキングが各種媒体で展開されていましたが、多くのランキングで本作をTOPに推す声が多く上がっていました。
家庭用ゲームを大きく普及させたハード、ファミコン。それに継ぐ後継機であるスーパーファミコンはドット絵と言う見降ろし型や横視点で展開されるゲーム文化に置いては、1つの頂点を築いた時代でありそのスーパーファミコンの時代に最も花形とも言えた人気ジャンルであったのがRPGというジャンルでした。
RPGはもともと海外のパソコンゲーム市場で密かに人気を得ていたものが国産の普及機であるファミコンに置いて大衆に、そして日本人向けに最適にカスタマイズされて人気を誇ったのがドラゴンクエスト。そのドラゴンクエストの影響も受けながらより派手に、またマニアックなシステムも導入しながら展開していったのがそのライバルと言われるファイナルファンタジーでした。
本作はそのドラゴンクエストの製作者である堀井雄二がプロットで、ファイナルファンタジーの製作者である坂口博信がディレクターに。そして、ドラゴンボールでお馴染みの鳥山明をキャラクターデザインに据えました。
実際には彼らの参加は初期プロットや大筋の調整に留まり、多くは当時のスクウェア社の若手が担っていた部分もあったようですが、音楽を担当したのが光田康成氏など、それすらいまとなっては層々たる面子だったのです。
時代の狭間も味方した豪華布陣と海外での異例の受容
それを500万部に達そうとしていた当時の週刊少年ジャンプのバックアップも受け大々的に広告展開、制作を手掛けたのはファイナルファンタジー以外にもロマンシングサガや聖剣伝説といったミリオンセラー級の人気RPGを手掛けていた最も勢いのあった時期のスクウェア。投入されたハードは今も日本のゲーム業界で多数の人気タイトルを掲げハード普及率(SWITCH)で牽引する任天堂のスーパーファミコン…
制作陣だけでなく、それを取り巻く環境も今考えたら凄い布陣です。これがあと1年ほどもずれていたらジャンプ本誌の部数は低下しており、次世代ハードのゴタゴタでゲームハードの提供源の任天堂と、ソフト開発のスクウェアは一時的に袂が別れてしまったので、本当に時代の狭間にドカンと投下された記念碑的一本だとも言えます。
日本のRPGは海外では文化や需要形態の違いから、普及の壁にさらされ苦戦していたと言われていますが、ファイナルファンタジー6と本作クロノトリガーを経て一定の知名度を獲得したと言われています。そして後に3D化したファイナルファンタジー7以降で一躍、海外でも有名なメジャーなスタイルになります。
その後、海外独自のオープンフィールド型RPGが主力になるに連れて、国産のRPGは徐々に存在感を失っていったのですが…ここ数年、海外産の大作ゲーム路線も製作費と開発ベースの遅れからジレンマが出てくるようになった影響もあるのか日本製RPGの再評価が起こっています、特に海外では本作がJ-RPGの原点のように語られる事が多く、日本のみならず海外での評価も未だに抜群に高いという異例の作品になっています。
FF的な文法で作られた戦闘システム
そんな今尚時代を越えて支持される本作、では肝心の中身の方はどのなのか…当時の2大RPGで見れば、ドラゴンクエスト3ではキャラクターの職業を選べるロールプレイの醍醐味がファイナルファンタジー5では特定の職業を育てると、その特技をアビリティとして個別に習得しキャラクターをカスタマイズするシステムなどが有名でした。
また同じスクウェア社でもロマンシングサガシリーズなどはキャラクターが戦闘中に取った行動で個別の能力を覚える熟練度システム。戦闘中にランダムに技を閃くひらめきシステムなどがありました。これらに比べると、カスタマイズや育成面では飛びぬけて大きな特徴は見られません。
ただし、初心者~中級者のプレイヤーに合わせた仕様になっていると思います。ファイナルファンタジーでは4作目で戦闘の流れに時間の概念を取り入れたアクティブタイムバトル方式を採用。キャラクターがコマンド入力中でも敵側の時間も動くため、アクションゲームのような臨場感、時間がカウントダウンしていく事による多彩な戦闘ギミックが楽しめます。
本作ではFFシリーズからこの戦闘方式を取り入れています。特にボス戦では1体1体に特徴がありパズル的な戦略が求められるものもあり、これはRPGに慣れた方でもなかなか手ごたえを感じることが出来る仕様になっています。
また魔法などもFFシリーズと同じ名前で統一されていますが、本家がシリーズが重なるごとに次第に数が増えていったものを絞り込んだ感があります。その一方でキャラクター固有の属性や特技、レベルが上がる毎に固有のキャラクター同士で発生する連携技が割り振られており、敵の技を覚えるキャラクター、アクセサリーによるアビリティの追加など、本家FFから有用なシステムが取り入れられています。
また、シームレスに移行する戦闘シーンや味方のコマンドのターンが一致した際に発動される連携技は令和現在のJ-RPGでもお馴染みの要素、複雑すぎないながらも戦闘に臨場感と爽快感を加味している、絶妙な要素と言えるでしょう。
ドラクエ的文法で彩られたストリーテリング
ドラゴンクエストを思わせる流れとして、本作は当時のスクウェア社のRPGの多くにある主人公のセリフは取り入れられていません。主人公クロノも仲間キャラクターたちと同じように多彩な動きを見せ、また仲間キャラクター達には豊富なサブイベントや人格面での個性も割り当てられていますが…クロノは戦闘面での個性以外はキャラクターの創造の範囲に留まる作りになっています。この点はドラゴンクエストの堀井雄二が最後までこだわっていた点だと言われています。
そして、ストーリー導入部の流れで時間をかけて本編のストーリーの軸や目的、戦闘の流れを理解できるチュートリアルのような作りになっているのですが、チュートリアルを本編と分離させずに、ストーリーと連動させていく手法は実にドラクエ的。また中世の魔王vs勇者という流れはそのままドラクエの世界をパッケージした流れとも言えます。
魔王の部下たちもビネガー、マヨネー、ソイソーと食卓でお馴染みの名前で統一、そして勇者がカエル…このあたりは鳥山明センスがさく裂しているあたりかもしれません。
本作では自然な描写が特に美しく、今では当たり前になっていますが移動場面と戦闘場面も切り替えがなくシームレスな流れになっています。この辺りは同じスクウェア社の聖剣伝説シリーズを彷彿とさせます。
歴史を又にかけた壮大な流れを売りにしている本作は、舞台が現代~中世~未来~原始~古代と次々に入れ替わっていきます。1度訪れた時代もストーリー的に再度訪れることになり、特に中世編~原始篇はほぼ連続してクライマックスの展開がつづくため、ストーリーのテンションを維持したまま絶妙にスライドしていきます。
中盤以降のメインと言える古代編はスクウェア社お得意の込み入ったストリーテリングになり、続編クロノクロスにも連なるストーリー。ただ、この歴史を積み重ねていく事で人類の進化や古代文明が大きくクローズアップされるどこかアカデミックな感覚は、ドラクエのエニックス社がリリースしたガイア幻想記や天地創造などのクインテット製RPGを思わせるものでもあります。
積み重ねられたJ-RPG的な文法
そして各時代で1人づつ仲間が増えていき、最終的に星の運命をかけた最大の敵との対決に突入していきます。ストーリーがクライマックスに突入した段階で、どの時代も自由に行き来できるようになり、各時代・各キャラクターのサブイベントが一挙に解放される。これはファイナルファンタジーシリーズお馴染みの要素です。
各時代には意味深な封印された宝箱がありそれも終盤で解放されますが、こちらはドラゴンクエストでいう「最後の鍵」的なギミック。終盤で各地を周りながら記憶を頼りに宝箱を解放していく楽しさでもあります。
そして、本作でも語り草となるマルチエンディング方式と強くてニューゲーム。一度ゲームをクリアするとそのデータを引き継いで再開できることと、そのシステムを引き継いでどのタイミングでもラストボスに挑むことが出来て、それによって様々なエンディングを迎えることが出来ます。これが本編クリア後も引き続き楽しめる要素の1つとなっています。
マルチエンディングや強くてニューゲームは本作が初出ではありませんが、その要素を大きく打ち出し、ユーザーに大きなインパクトを与え一般化させたのは本作の功績でしょう。
現在遊ぶには…
大変な人気作でありながら、いまだに明確なリメイクが出ていない本作。steamではリマスター版が配信されています。スマホではi-osとアンドロイド版がリリースされています。
PS系ハードではPS3、vita、PSPでゲームアーカイブス版が配信されており、PS1,2,3ではPS1版のクロノトリガーを遊ぶことが出来ます。DS&3DSではDS版でもプレイ可能。現役の家庭用ハードではsteam配信とスマホ配信に留まる為、switch2やPS5でのリリースなり配信があると嬉しいのですが、いまだにアナウンスは聞こえてこない現状、そこが残念ではあります…
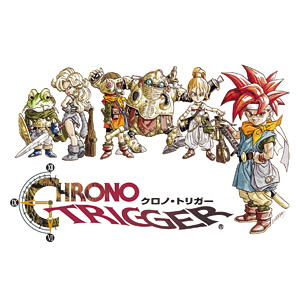
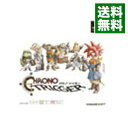
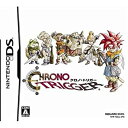

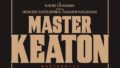
コメント